
ガイド
発達障害と愛着障害(反応性アタッチメント症、脱抑制型対人交流症)の関連性や違いとは?訪問看護ステーションを経営する医師が解説
発達障害と愛着障害(反応性アタッチメント症)は、子どもの成長に大きな影響を与える重要な課題です。発達障害についての知見は2010年代後半から広く知られ始めていますが、愛着障害(反応性アタッチメント症)については情報が少なく、また誤解も存在しているようです。さらに、発達障害と愛着障害(反応性アタッチメント症、脱抑制型対人交流障害)の関連性や違いについても、注目が集まり始めています。
2024年には、NHKスペシャルでアタッチメントについての特集が放送され、大きな反響を呼びました。
外部リンク:アタッチメント “生きづらさ”に悩むあなたへ – NHKスペシャル
本記事では、最新の研究データと専門家の見解をもとに、両障害の特徴、関連性や違いについて詳しく解説します。また、児童精神科の訪問看護ステーション・ナンナルのアプローチを紹介し、子どもたちの育ちを支える方法を探ります。
発達障害と愛着障害(反応性アタッチメント症、脱抑制型対人交流症)の定義と特徴

発達障害の定義と主な種類
発達障害は、脳の発達に関わる生物学的要因と環境との相互作用によって引き起こされる一連の障害を指します。アメリカ精神医学会による診断基準「DSM-5」では、「神経発達症」「神経発達障害」と表記されます。
日本の厚生労働省の調査によると、通常の学級に在籍する小中学生の8.8%に発達障害の可能性があるとされています。
参考:通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果(令和4年)について
主な発達障害の種類と特徴
- 自閉スペクトラム症(ASD)
社会的コミュニケーションの困難、限定的な興味と反復的な行動など - 注意欠如多動症(ADHD)
不注意、多動性、衝動性など - 限局性学習症(LD)
読み書き、計算など特定の学習領域の困難など - その他
トゥレット症候群、吃音など
愛着障害(反応性アタッチメント症、脱抑制型対人交流症)の定義と形成過程
愛着障害(反応性アタッチメント症)は、幼少期の重要な他者との関係性の中で形成される愛着(アタッチメント)に問題が生じた状態を指します。アメリカ精神医学会による診断基準「DSM-5」では、「反応性アタッチメント障害」「反応性愛着障害」、「脱抑制型対人交流障害」と表記されます。また、最新の「DSM-5-TR」では「反応性アタッチメント症」「脱抑制型対人交流症」と表記され、本記事ではこちらを使用しています。
ナンナル代表・岡琢哉(精神科医)
愛着障害という言葉は、日常的に使用される「愛着」という言葉から誤解を招きやすい側面があります。愛着(アタッチメント)は、人間が危機から逃れ、安全、安心を得るために必要な関係性を指す概念です。英語の “attachment” が日本語に訳されて「愛着」となりましたが、この訳語が「愛情」という意味合いを強く感じさせてしまう原因となっています。実際には、アタッチメントは「付属物」や「接着している」といったニュアンスに近く、必ずしも愛情の有無を意味するものではありません。
愛着障害(反応性アタッチメント症)の形成要因:
- 養育者の不在や頻繁な交代
- 虐待やネグレクト
- 養育者の精神疾患や依存症など
【コラム:愛着理論の歴史】
愛着理論は、イギリスの精神分析学者ジョン・ボウルビィによって提唱されました。第二次世界大戦後の戦災孤児の行動観察から生まれたこの理論は、人間の発達における初期の人間関係の重要性を強調しています。

発達障害と愛着障害(反応性アタッチメント症、脱抑制型対人交流症)の症状と見分け方
発達障害の主な特徴
発達障害には以下のような特徴が見られます。
- コミュニケーションの困難
言語理解や表現の問題、非言語コミュニケーションの困難 - 社会性の問題
他者との関係構築の困難、社会的ルールの理解の難しさ - こだわりや興味の偏り
特定のテーマへの強い興味、日常の決まりへのこだわり - 注意力や集中力の問題
集中の持続困難、複数の課題の同時処理の難しさ - 行動や感情制御の問題
静止することや不快な刺激に対する反応が過剰、衝動的な行動、感情の調整が難しい - 学習の困難
特定の学習領域(読み書き、計算など)での顕著な困難
愛着障害(反応性アタッチメント症)の主な特徴
愛着障害(反応性アタッチメント症、脱抑制型対人交流症)の特徴には以下のようなものがあります。
- 感情的引きこもり
養育者に対して慰めを求めたり、応じたりする行動がほとんど見られない - 情緒の不安定さ
他者に対する最小限の対人交流と情緒的反応、限られた陽性感情の表現が見られる - 説明しがたいイライラや恐怖
養育者との穏やかな交流中にも説明できないいらだたしさや恐怖が突然現れることがある - 過度な社交性
見慣れない大人に対して、ためらいなく近づき、過度に馴れ馴れしい言語や身体的行動を示す - 境界設定の欠如
新しい環境でも養育者を振り返って確認することなく、自分の行動を続ける - 他人について行くことへのためらいの欠如
ほとんどためらいなく、見知らぬ大人について行こうとする
【コラム:アタッチメントスタイルについて】
アタッチメントスタイルは、幼少期に主要な養育者との関係を通じて形成される、他者との関係性における一貫した行動パターンを指します。
主なアタッチメントスタイルには、安全型、不安型、回避型などがあり、それぞれが異なる対人関係の取り方を反映しています。
アタッチメントスタイルは、必ずしも病的ではなく、親子間の関係性や生活環境によって変化し得るものです。それにもかかわらず、不安型や回避型アタッチメントを示す子どもが、誤って愛着障害と診断されたり、過度に病理化されたりするリスクがあります。アタッチメントスタイルと愛着障害を正しく区別することは、子どもに対する適切な支援を提供するために非常に重要です。

両障害の類似点と相違点
愛着障害と発達障害は異なる障害ですが、似た部分もあるため、正確に区別することが重要です。まず、発達障害は、脳の発達や遺伝的要因によって引き起こされるもので、社会的相互作用やコミュニケーションに持続的な困難を伴います。特に自閉スペクトラム症(ASD)では、他者との交流や言葉の理解が難しいことが特徴です。
一方、愛着障害は、幼少期に極端な社会的ネグレクトや不安定な養育環境が原因で発生します。代表的な例として反応性アタッチメント症(RAD)や脱抑制型対人交流症(DSED)があります。これらの障害では、親や養育者との安定した関係を築くことができず、感情的な引きこもりや他者に対する過度な馴れ馴れしさが見られます。
類似点
- 社会的な困難
どちらの障害でも、他者との関係に困難を抱えることがあります。ASDでは他者とのコミュニケーションが苦手であり、RADやDSEDでは親との適切な関係が築けないことが共通しています。 - 行動の異常
どちらの障害でも、一般的な子どもと比べて行動に異常が見られます。ADHDでは衝動的な行動が見られ、DSEDでは他者に対する馴れ馴れしさが特徴です。
相違点
- 原因の違い
発達障害は脳の発達や遺伝に関連するものであるのに対し、愛着障害は養育環境の影響によるものです。 - 行動の対象
発達障害では広範な社会的困難が見られるのに対して、愛着障害では特に親や養育者との関係に問題が集中しています。 - 診断の方法
発達障害は遺伝的な要因や脳の発達の観点から診断されるのに対し、愛着障害は子どもがどのように育てられてきたかが診断の大きな要素になります。
注意点
特に、ASDとRADの区別は難しいことがあります。ASDは神経発達に基づく広範な社会的困難を示しますが、RADは養育者との適切な愛着が形成されないことで生じます。また、ADHDとDSEDの区別も重要です。ADHDは衝動性や注意力の欠如が主な症状で、DSEDは社会的な境界設定の欠如や見知らぬ大人に対する過度な馴れ馴れしさが特徴です。これらの障害の診断では、子どもの生活環境や行動の背景を詳細に評価し、誤診を避けることが必要です。

発達障害と愛着障害(アタッチメント)の関連性と併存可能性
発達障害と愛着障害は、子どもの発達における異なる障害ですが、いくつかの点で関連性があり、診断において注意が必要です。
発達障害(特に自閉スペクトラム症:ASD)は、神経発達に関連する障害で、遺伝的要因や脳の発達に起因し、社会的相互作用やコミュニケーションに持続的な困難を伴います。
これに対し、愛着障害は、幼少期の極端な社会的ネグレクトや不安定な養育環境によって引き起こされ、養育者との関係性に深刻な問題が生じる障害です。代表的な愛着障害には、反応性アタッチメント症(RAD)や脱抑制型対人交流症(DSED)があり、これらはDSM-5-TRにおいて定義されています。
RADとDSEDの診断には、ASDの診断を除外することが求められるため、理論的にはASDと愛着障害は併存しないとされています。しかし、実際には、ASDを持つ子どもが安定型以外のアタッチメントスタイル(不安型や回避型)を持つことが多いことが研究により示されています(Rutgers et al., 2004)。このため、ASDの子どもが誤って愛着障害と診断されるリスクが高まる可能性があります。
ASDの子どもは、他者との関係性を築くのが難しく、特に親や養育者との関係が課題となることが多いため、RADやDSEDと混同されることがあります。例えば、ASDの子どもが感情的に引きこもったり、他者に対して過度に馴れ馴れしい行動を示す場合、それが愛着障害として誤解される可能性があります。
したがって、ASDの診断が行われる際には、子どものアタッチメントスタイルや親との関係性を詳細に評価し、愛着障害との誤診を避けるための慎重な診断が求められます。これにより、適切な支援と介入が行われ、子どもの健全な発達が促進されます。
参考文献
Rutgers, A. H., Bakermans-Kranenburg, M. J., van IJzendoorn, M. H., & van Berckelaer-Onnes, I. A. (2004). Autism and attachment: A meta-analytic review. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45(6), 1123-1134.https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-7610.2004.t01-1-00305.x
診断と評価:専門家への相談の重要性
発達障害と愛着障害(反応性アタッチメント症)の正確な診断と評価には、多面的なアプローチが必要です。
診断プロセス:
- 詳細な問診:家族歴、発達歴、現在の症状など
- 行動観察:構造化された環境と自然な環境での観察など
- 心理検査:知能検査、発達検査、社会性検査など
- 身体面の検査:必要に応じてMRIの画像検査、血液検査など
早期診断の重要性:
- 適切な支援の早期開始
- 二次障害の予防
- 家族の理解と受容の促進
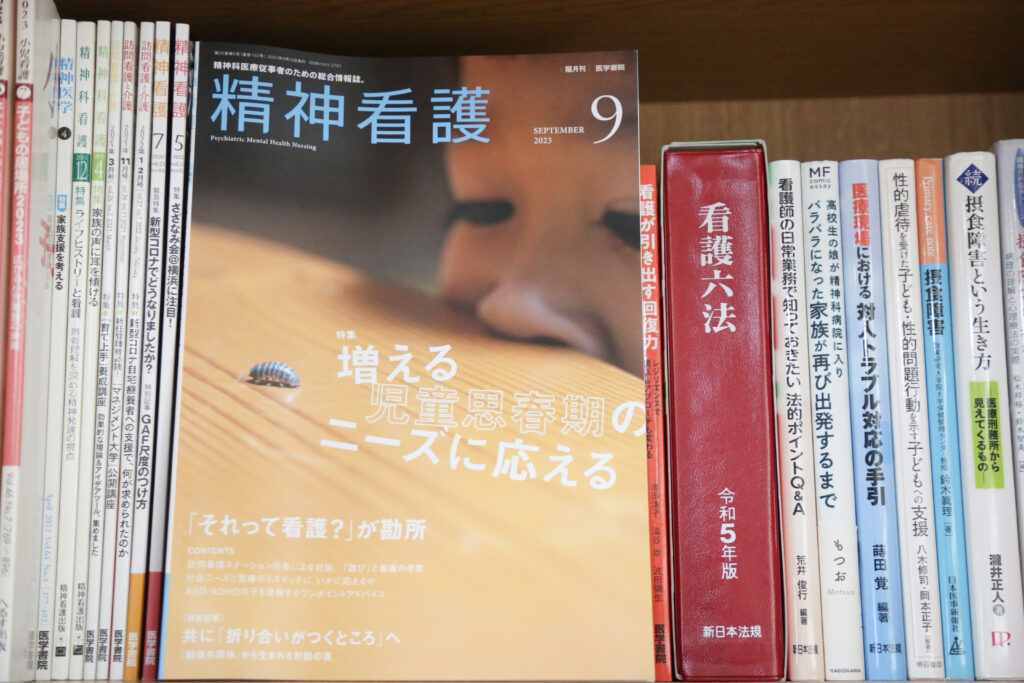
専門家による支援:ナンナルの児童精神科訪問看護の特徴
ナンナルの児童精神訪問看護は、発達障害や愛着障害(反応性アタッチメント症)を持つ子どもたちとその家族に対しても支援を提供しています。
ナンナルのサービスの特徴
- 家庭環境でのサポート
訪問看護は子どもの安心できる家庭環境で行われ、ストレスを軽減しながら、日常生活における適応力を高めます。 - 包括的なケア
ナンナルの訪問看護では、子どもだけでなく、家族全体の心理的サポートも提供し、家族全員が共に成長できるよう支援します。 - 早期介入の重要性
子どもの発達や行動における早期の問題発見と対応が、将来的な発達障害や精神的問題の悪化を防ぐために重要とされています。 - 個別化されたケアプラン
ナンナルでは、各家庭や子どもの状況に応じて個別にカスタマイズされたケアプランを作成し、継続的なモニタリングと調整を行います。 - 多職種連携
かかりつけの小児科医や精神科医、医療機関や教育機関のソーシャルワーカーなどの専門家と連携し、子どもに最適な支援を提供する体制を整えています。 - 地域社会との連携
地域のリソースや支援機関と協力し、子どもと家族が地域社会で健やかに暮らせるよう、包括的なサポートを提供します。
発達障害と愛着障害(反応性アタッチメント症)への支援アプローチ
ナンナルの訪問看護サービスでは、複合したケースにも柔軟に対応し、子どもと家族に最適な支援を提供しています。「遊び」を重視していることも特徴のひとつです。
作業療法士Uさん:
僕らが用意したもので遊ぶよりも、子どもたちが好きなもの、興味あるものに乗っかって一緒に遊ぶ方が、関係は作りやすいと思います。
子供たちの自然な会話、自然な思いを引き出すのに、遊びは有効だなと感じる場面はありますね。
テレビゲームやカードゲームもよく使いますが、作業療法士としては体を使うことも意識したいと思っています。室内でできる「風船バレー」や「ボールダーツ」のような運動は、自宅でもできるので、よく取り入れています。

よりよい環境づくりのための家族支援と周囲の理解
発達障害や愛着障害(反応性アタッチメント症)のある子どもを育てる家族への支援は、子どもの成長に大きな影響を与えます。
家族支援の重要性
- 養育者のメンタルヘルスケア
- きょうだい児への配慮
- 家族全体のレジリエンス(回復力)の強化
訪問看護における家族支援の重要性については、下記の記事で解説しています。
内部リンク:訪問看護における家族支援の重要性と実践
家族支援アプローチ
- 心理教育 障害についての正確な知識提供
- ペアレントトレーニング 効果的な養育スキルの習得支援
- レスパイトケアの調整 養育者の休息確保
- 家族療法 家族システム全体の機能向上
- サポートグループの紹介 同じ経験を持つ家族との交流促進
訪問看護師で認定看護師のMさん:
「この期間があったから良かった」と思えるような支援を少しだけ一緒に考えることに、家族支援の意味を感じます。家族だけでは、そのような思いになるのは、難しい場合が多いからです。
困難を抱えているお子さんの支援で行き詰まっているご家庭の中に、「それでいいんだよ」という立場の人が入るだけでも、 風通しは変わってくると実感しています。ですから家庭内に入る意味は大きいと思います。
訪問看護師Tさん:
親御さんに、「同じ方向を向いているんだ」「同じように考えてるんだ」「この支援でいいんだ」と感じてもらうことを大事にしています。
そして、子どもが動き出すチャンスがきたときに、一緒に背中押してあげる。そうできたときが一番スムーズな流れだと思います。

正しい理解と適切な支援のために
発達障害と愛着障害(反応性アタッチメント症)は、それぞれ異なる特徴と課題を持つ障害ですが、適切な理解と支援により、子どもたちの可能性を大きく広げることができます。
重要なポイント
- 早期発見・早期支援の重要性
- 正確な診断に基づく個別化された支援計画
- 家族全体を視野に入れた包括的アプローチ
- 社会全体での理解と受容の促進
ナンナルの児童精神科訪問看護は、これらの重要ポイントを全て押さえた支援を提供しています。専門的な知識と経験を持つ看護師や作業療法士が、子どもたちの生活の場に直接訪問し、個別化された支援を提供します。発達障害や愛着障害(反応性アタッチメント症)のある子どもたちが、その主体性を尊重されながら、自分らしく成長していける環境づくりを実現していきます。
発達障害や愛着障害(反応性アタッチメント症)のある子どもたちの支援に興味がある看護師・作業療法士の方々へ
現在、一緒に子どもたちを支える看護師・作業療法士を募集しています。ナンナルでは、経験豊富な先輩看護師のサポートや充実した研修制度により、未経験からでも安心してスタートできる環境が整っています。新しいキャリアにチャレンジしたい方は、ぜひナンナルの求人をチェックしてみてください。
すぐに転職できなくてもOKです。まずは30分程度のカジュアル面談(オンライン)ができるので、お気軽にご連絡いただき、ナンナルのことを知っていただければと思います。
お問い合わせ・お申し込みはこちら
監修:ナンナル代表・岡琢哉(精神科医)
編集:株式会社ぺリュトン


