
ガイド
子どもの不安症(不安障害)の種類、原因、症状、対処法【児童精神科医監修】
子どもの不安症(不安障害)に、近年注目が集まっています。本記事では、子どもの不安症について、その種類や原因、症状、年代ごとの特徴などを詳しく解説します。
不安は誰もが経験する感情ですが、それが日常生活に支障をきたす程度になると、専門家のサポートが必要になることがあります。子どもの不安症は、単なる「心配性」や「臆病」とは異なる、医学的に定義された精神障害です。よく知られている「パニック症」や「広場不安症」も、不安症に含まれます。不安症は、子どもの友人関係の困り感、自尊心の低下、学業成績の低下など、さまざまな困りごとを引き起こす恐れがありますが、適切な理解やケアがあれば、状況が改善する可能性があります。
本記事を通じて、子どもの不安症への理解が深まり、育ちを適切にサポートするヒントを得ていただけたら幸いです。
不安症(不安障害)とは

不安症は、過度の不安や恐怖を特徴とする精神障害の一群です。
全ての人がときに不安を感じることはありますが、不安症の場合、その不安が長期間続き、日常生活に支障をきたすレベルに達します。
日常的に感じる不安と病的な不安は、地続きなのが難しいところです。不安という感情は、人間にとって重要な防衛機能の一つであり、不安が特に高まったときには感覚が過敏になるという特徴があります。
例えば、人間がサバンナのような危険な環境に置かれた場合、不安を感じないことのほうがむしろ危険です。その環境下では、聴覚が鋭くなったように感じられるのは自然な反応であり、警戒を緩めることは生命の危機に直結します。不安が強まる状況とは、自身に危険が接近していることを示すシグナルです。そのため、神経が自然と過敏になり、周囲の危険をより早く察知できる状態へと移行します。これは生存のための重要な適応メカニズムといえます。
一方で、安全が確保されているはずの環境において過度の感覚過敏が生じる場合、それは問題となり得ます。例えば、安全な自分の部屋にいるときに強い不安を感じる状態は、通常の範囲を逸脱している可能性があります。本来はくつろげるはずの状態でも常に不安があり、過敏な状態だと、非常に疲れやすくなることも問題です。
日本における子どもの不安症の現状は深刻です。文部科学省の調査によると、小中学生の不登校の原因の23.1%が「不安・抑うつ」に関連しているとされています。
不安症には、限局性恐怖症、分離不安症、社交不安症、全般性不安症、パニック症、広場恐怖症なども含まれます。
参考外部リンク:文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」
子どもの不安症(不安障害)の原因
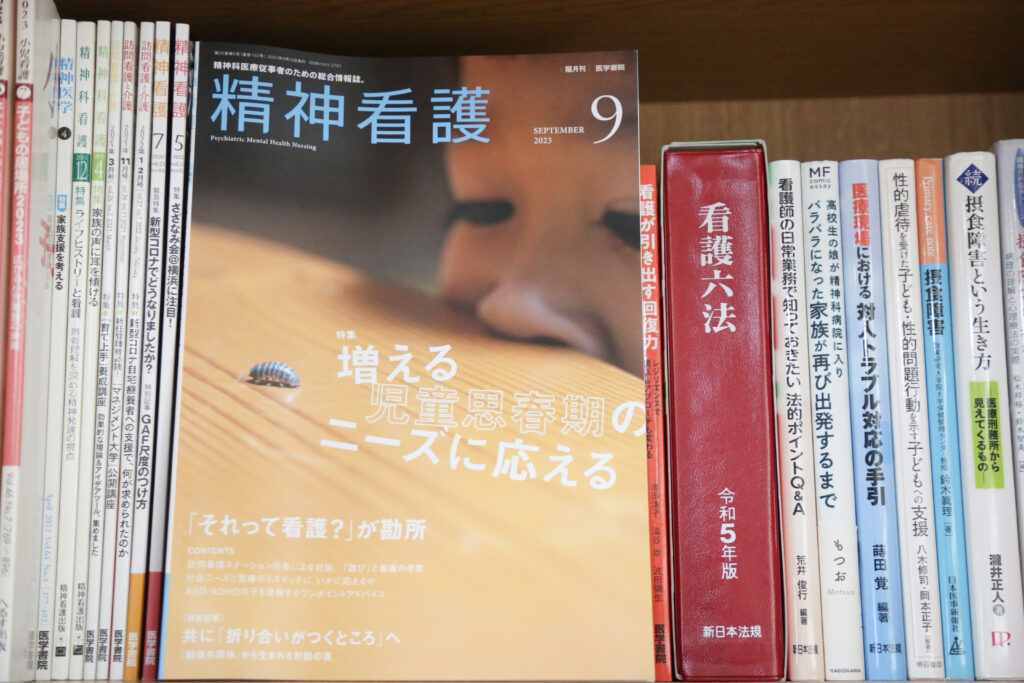
子どもの不安症の原因は複雑で、単一の要因ではなく、複数の要因が絡み合って発症すると考えられています。生理学的要因、環境要因について解説します。
生理学的要因
不安を引き起こす生理学的要因として、まずは扁桃体が大きな役割を持っています。
扁桃体は、脳の中では古い脳と言われています。人間の扁桃体は他の動物より大きいのですが、小さな動物でも持っている部位です。扁桃体は情動反応の処理と記憶に関わり、危険を認識する場所です。
扁桃体が危険を察知したあと、脳内になる視床下部がホルモンを出し、胸がドキドキしたりします。視床下部は、ホルモンを出し、自律神経の調節も担っています。
扁桃体が反応した後に、視床下部からホルモンが出て、胸がドキドキするという一連の動きが、不安を感じたときの生理学的な動きです。これが、不安症と診断されない人でも誰もが持っている機能です。怖いと感じることにちゃんと対処できるよう、緊急モードに切り替わる脳の仕組みになっているのです。
誰もが持っている機能ですが、過度になると不安症と診断される可能性があります。例えば、ストレスフルな環境に長期間さらされることで、脳の構造や機能に変化が生じ、不安症の素因が形成される可能性があります。
子どもの不安症(障害)の種類と発症時期
子どもの不安症は、発達段階に応じて異なる形で現れることがあります。各年齢層で典型的に見られる不安症の種類を紹介します。
幼児期(小学校入学前)
幼児期に見られる主な不安障害には、以下のようなものがあります:
1. 限局性恐怖症
特定の物や状況に対する強い恐怖
例:動物恐怖症、雷恐怖症、暗闇恐怖症
症状:対象に遭遇すると激しい泣き叫びや、固まってしまうなどの反応
2. 分離不安症
養育者から離れることへの過度の不安
症状:保育園や幼稚園で泣き叫ぶ、一人で寝られない、養育者の外出時に強い不安を示す
この時期の子どもは、自身の感情を言葉で表現することが難しいため、身体症状(腹痛、頭痛など)や行動の変化(癇癪、退行など)として不安が現れることがあります。
小学生期
小学生期になると、より複雑な不安障害が現れることがあります:
1. 社交不安症
人前での行動や発言に対する過度の不安
症状:授業中の発表を極度に恐れる、友達との交流を避ける、給食を食べられないなど。特に思春期前後で顕著になることが多い
2. 全般性不安症
さまざまな事柄に対する過度の心配や不安
症状:学業、友人関係、家族の健康など、多岐にわたる心配が止まらない
この時期は学校生活が中心となるため、不安障害が学業成績や友人関係に大きな影響を与える可能性があります。
思春期以降(中高生)
思春期以降になると、より成人に近い形の不安障害が見られるようになります:
1. パニック症
予期せぬパニック発作が繰り返し起こる
症状:動悸、発汗、震え、窒息感などの身体症状を伴う突然の強い不安
2. 広場恐怖症
逃げ場がない場所や状況への恐怖
症状:電車や人混みを極度に恐れ、外出を避ける
この時期は、学業や進路の問題、対人関係の複雑化など、ストレス要因が増加するため、不安障害が悪化または顕在化しやすい時期でもあります。
各発達段階で見られる不安症の特徴を理解し、適切に対応することが重要です。また、これらの不安症は年齢とともに形を変えたり、複数の不安症が併存したりすることもあるため、継続的な観察と柔軟な対応が求められます。
子どもの不安への対処方法

子どもの不安への対処方法を考える上で、まず大切なのは「対処できる不安」と「対処できない不安」があることです。例えば「明日の入学式で友達ができるかな」という不安は、「明日」を過ぎたらもう不安ではなくなります。一方で「いつか死んでしまうのが不安」となると、考えても対処できません。
その不安が対処できるものなのかどうかを見極めて、対処できる不安とひとつずつ向き合っていくのが大切です。その際、保護者などの大人が適切に関わることは重要となります。
そして、過剰に不安になってしまう場合は、病院などの専門家を頼ってください。
不安への対処法(3ステップ)

1.不安の内容を明確にする
子どもの言葉で不安を表現してもらい、具体的な状況や感情を一緒に探ります。子どもが1人で取り組むよりも、周囲が適切に関わり、一緒に考えていくことが大切です。
2.対処できる不安から対峙する
現実的に対処できる不安と、不確実な未来への不安を分け、対処できる不安から対峙していきます。
3.不安を乗り越えた経験を力にする
周囲の人の力を借りながら、不安を乗り越え、その経験を糧にしていくことも重要です。ただし、具体的な症状が出ている場合には無理をせず、医療機関にかかってください。
これらのステップを通じて、子どもが不安に直面したときに適切に対処できる力を育てることができます。
不安症を抱える子どもたちを一緒に支えませんか?

不安は誰しもが持っているメカニズムであり、本来は重要なものです。しかし、それが過剰になってしまうと、社会生活に支障をきたしてしまうことがあります。ただ、不安症は決して珍しいものではなく、多くの子どもたちが経験し、そして改善させています。適切な支援と治療により、子どもたちが自信を持って社会へ出ていくことも可能です。
児童精神科の訪問看護ステーション・ナンナルでは、本人のケアはもちろんのこと、環境に対してもアプローチしています。
現在、一緒に子どもたちを支える看護師・作業療法士を募集しています。ナンナルでは、経験豊富な先輩看護師のサポートや充実した研修制度により、未経験からでも安心してスタートできる環境が整っています。新しいキャリアにチャレンジしたい方は、ぜひナンナルの求人をチェックしてみてください。
すぐに転職できなくてもOKです。まずは30分程度のカジュアル面談(オンライン)ができるので、お気軽にご連絡いただき、ナンナルのことを知っていただければと思います。
お問い合わせ・お申し込みはこちら


